|
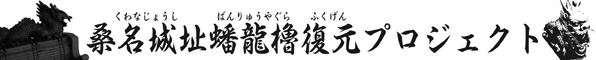
蟠龍とはこれから天に昇ろうとする踞(うずくま)った龍の事を指します。幻獣である龍は古来より中国を始め諸国で神聖なる生き物としてあがめられてきました。日本でも水神として船の往来の安全や日照りや洪水から守ってくれる尊神として様々な場所でこの姿を見ることが出来ます。
三重県にある桑名城址には側を流れる揖斐川を利用した水城でこの城には95もの櫓がありました。その中でも蟠龍櫓は川口にある七里の渡しに面して建てられており、有名な浮世絵である東海道五十三次にも桑名の名所として描かれています。
また享和二年(1802年)刊の「久波奈名所図会」によるとこの有名な単層入母屋造りの蟠龍櫓の屋根の上に「蟠龍瓦」と書かれてあり、当時すでにこの瓦が設置してあったことを物語っています。加えて文化三年(1806年)刊の書物には「臥龍の瓦は当御城門乾櫓上にあり、この瓦名作にして龍影水にうつる。ゆへに、海魚往ずといへり。」とあり名作「蟠龍瓦」が東海道を往来する人の目を楽しませていたのがわかります。
このたび水門統合管理所を建設するに当たり、その建設場所がこの蟠龍櫓跡地近辺でもあったことから復元プロジェクトが発足、長き工事の末、平成15年3月に完成いたしました。
その際、この名物「蟠龍瓦」も復元されることになりその名誉ある復元作業に弊社が光栄にも指名されたのです。
以下に蟠龍瓦が復元されるまでの行程を記したいと思います。
|

|
【荒成型】
製作開始から7日
良質な三河粘土を使用し、蟠龍の外観を全て手作業で成型して行きます。全体のバランスがこの過程で決まります。現在の状態から仕上げ>乾燥>焼き上げの工程で約一割収縮します。
|
|

|
【荒仕上げ】
製作開始から10日
蟠龍の精悍な顔、胴体、足の勢いを荒仕上げの中で表現しています。
|
|

|
【頭部を細工】
製作開始から12日
角から髭、口元廻りを金ヘラ等で表現。背ヒレの輪郭構成をします。
|
|

|
【製作過程の検査】
蟠龍の首、尻尾に付いている布は粘土の乾燥を調整する為に被せてあります。粘土は細い部分から乾燥していまいますので乾燥切れを防いでいます。
|
|

|
【龍鱗貼り1】
製作開始から18日
一枚一枚手作業で花びらのような龍鱗を貼り付けていきます。尾の方から付けなければメリハリのある模様に仕上がりません。
|
|

|
【龍鱗貼り2】
製作開始から25日
胴体まで龍鱗が貼れました。角の先端は乾燥が始まっています。
|
|

|
【本乾燥】
製作開始から40日
全体を均等に乾燥させます。工程上で一番神経を使う所です。
|
|

|
【乾燥終了】
製作開始から60日
窯入れ直前の状態。
|
|

|
【焼き上げ1】
製作開始から70日
慎重に窯に入れ、徐々に温度を上げ、最高摂氏1150度の高温で約4日焼き上げ、また徐々に温度を下げます。いぶし瓦には摂氏1150度まで温度を上げた後に燻化作業により『いぶし銀色』を付けます。
|
|

|
【焼き上げ2】仕上がり確認
|
|

|
【棟上げ】
|
以下は同時に設置された他の瓦の制作風景です。
|

|
【製品検査】
鬼瓦上部に取り付ける瓦です。「立葵紋入り鳥伏間瓦」の乾燥中の状態です。
|
|

|
【製品検査】
|
|

|
【製品検査】
「立葵紋入り城鬼瓦」の乾燥中の状態です。
|
いかがでしたでしょうか。このような特殊な案件もお引き受けできるのは、弊社の技術力の高さと物事に対する発想力が認められているからだと思います。
当初、復元プロジェクト最大の難関であった蟠龍の姿を文献や貴重な資料から考察、復元して今ある姿に出来たのも国内屈指の技術力を持つ瓦師との深い繋がりをもつ弊社だからこそ出来たのです。弊社の技術力は全国に渡って発揮されています。
<TOPページに戻る>
|